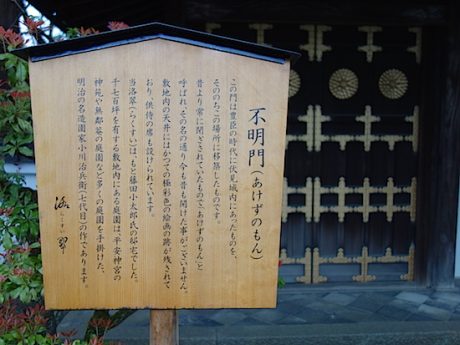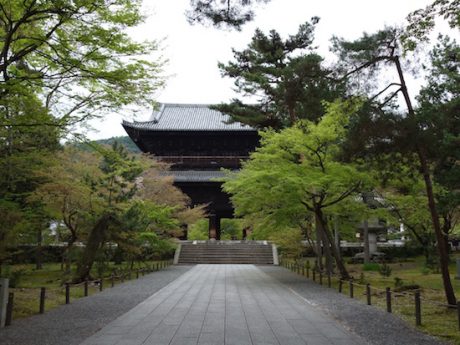竹の軒樋
京都にある茶室や数寄屋では、竹を半割りにして
樋として使う事例がよく見られます。
どこにでもある竹という素材を使ったストレートな表現ですが
素人のセルフビルドとは一線を画すセンスが感じられます。

こちらは苑路の縁に使われたクヌギの皮付き丸太
自然のものに最小限の手を加えるだけで、
ありふれた素材を無造作に使ったように見せています。
よく公園などに使われているのはフェイク(擬木)ですが
これは正真正銘のホンモノ。
クヌギは結構硬い木なので丈夫なのかと思い、係の人に聞いてみると
実際にはそんなに長持ちするものじゃないそうです。
竹にしてもクヌギにしても自然のものは朽ちてしまうので
手入れや交換に絶えず手間がかかります。
正確で丈夫で手入れの楽なものは今ではいくらでも手に入りますが
残念ながらそれらには文化の香りがありません。
ありふれたものにわざわざ手間をかける、
合理性の対極にこそ、日本文化の本質が香り立ちます。
2017.7.14 設計事務所 TIME