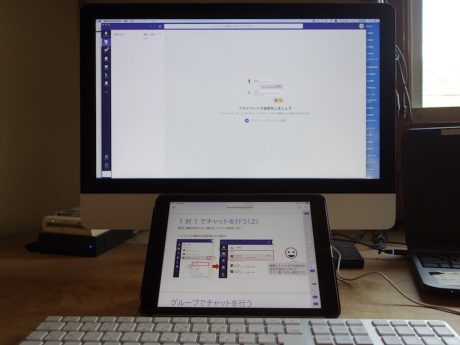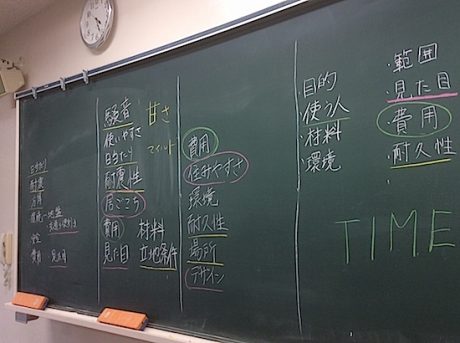重要文化財、旧毛利家本邸画像堂の保存修理工事
ヘリテージマネージャーを対象にした工事見学会に参加しました。
大正7年、自然の森を切り開いて造営された画像堂、
長年にわたり木々の落ち葉が屋根の排水を妨げ
雨漏りで傷んだ建物をこのたび修理することになったそうです。

建物は背の高い内陣(写真左端)のまわりに庇状に外陣が取り囲む形状。
外陣のしっくい壁部分に耐震補強を施し、仕上げ直しているそうです。

内陣を構成する骨組みは漆状の塗りを施し、黒光りする独特の表情、
床も黒を基調にした研ぎ出し仕上げで
伝統的な空間様式の中にも大正時代の近代的なセンスが見られます。

吹抜けた内陣上部の欄間には四周全体にガラス障子がはめ込まれ、
ハイサイドライトのように光が空間に降り注ぐ仕組みです。
この辺りのデザインにも、和の空間性とは異なる指向性があり
西洋建築にある垂直方向の特徴が見て取れます。

外陣部分の傷んだ屋根は吹き替え工事中
瓦の下地は土ではなく杉皮で、構造的な軽量化を考えていたのかどうか・・・
いずれにしても、湿潤な日本の気候に適した自然素材が生かされています。

内陣の宝形屋根
甍の生み出す優美な表現は和の伝統が生かされています。
それにしても、デジタルな機械がない時代に
三次元の造形をたくみに生み出すアナログの職人技はやはりすごい。

外陣、屋根垂木の間に通気抜きが設けてあります。
このあたりは、設計者による科学的な思考を感じます。
真壁構造や構造上の組み物、格子などのパーツなど
基本的な様式は和の伝統を引き継ぎながらも
明治以降に入ってきた西洋文化をアレンジしながら
伝統と現代性(時代性)との間での試行錯誤した姿が垣間見られます。
伝統は単なる過去の遺物ではなく、現代の文化にも確実につながっていることを
大正時代の設計者は今以上に意識し、時代の本質をつかもうとしたように思えます。
それは、単に新しいだけで無造作にデザインされがちな現代建築に勝る深みをもっています。